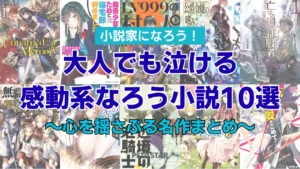第八章:ラプラス戦争編 ― 世界の命運を背負って
ルーデウスが立ち向かうのは、ただの“強敵”ではなかった。
人神のささやきは、その場しのぎの甘い言葉で人と人の間に亀裂を生み、ラプラスが残した負の遺産は魔族と人族の憎しみや古い戦争のしこりを残し続ける。さらに各国は王位や利権をめぐって争い、思惑を重ねている。これらが絡み合えば、また世界は戦火に包まれてしまう。だからこそルーデウスは「家族を守る」ために、世界の仕組みそのものを変える決意を迫られるのだった。
死にかけた末に出会った龍神オルステッドと、ルーデウスは同盟を結ぶ。目標は同じ――人神の筋書きを壊し、二度と世界を戦争に巻き込まないこと。方法は現実的で、力押しではなく情報・制度・外交・産業を組み合わせる。何より、家族を犠牲にせず、人を道具にせず、復讐に走らないという線を守る。これは従属ではなく“勝ち方の約束”だった。学園や家庭で培った「段取り」や「役割分担」が、ここで世界規模へと広がっていく。
人神は「一番楽な近道」を示して人を惑わせる。短期的には助かっても、未来を壊す道だ。ルーデウスはその罠を避けるために、情報を複数のルートで確認し、うますぎる話は必ず検証して記録を残す。孤立しやすい者には役割と居場所を与え、一発逆転を狙わず小さな改善を積み重ねる。剣ではなく「仕組みの改善」で世界を変える――これが彼の掲げる“戦わずに勝つ”方法だった。
そのためには政治も避けて通れない。アスラ王国では、王位継承を力ではなく制度で通す仕組みを整え、治安と広報を同時に動かして暴発を抑える。西方教会とは正面からぶつからず、災害対策や救護活動で協力の糸口を作る。冒険者や商業ギルドには物流と市場の整備を促し、暮らしを底から支えさせる。「正義」を語るのは簡単だが、人をまとめるのは難しい。ルーデウスは“第三の道”を提示することで、敵も味方も極端に偏らない場を増やしていった。
戦場を変えたのは技術でもある。ナナホシの研究は転移や召喚を安全に行う仕組みを整え、ザノバの工房は天才の力を「誰でも使える道具」に変えていく。さらに防災や医療では避難経路や捜索記録を標準化し、失敗も次につなげる記録にする。派手な大魔法よりも、小さな改善を千回重ねる方が確実に前線を押し上げていく。これこそ“続けられる強さ”だった。
避けられない小競り合いもある。しかしルーデウスは「勝っても疲弊しない」戦い方を選ぶ。あらかじめ撤退ラインを決め、情報戦で「戦う必要そのもの」を減らし、防衛と復旧を同時に設計する。勝利とは敵を全滅させることではなく、翌日ふつうに生活へ戻れること――その定義を広めていった。
支えとなるのは家族だ。シルフィは帰る場所として心を落ち着けさせ、ロキシーは未知を解き明かし言葉にする道しるべとなり、エリスは必要な時だけ刃を抜く力の象徴となる。三人が三様の役割を担うからこそ家族は揺れに強く、子どもたちの成長は未来をルーデウス一人に背負わせない仕組みとなる。彼はもう「英雄になるために戦う」のではなく、「暮らしを続けるために世界を整える」段階へと進んでいた。
しかしラプラスの影は消えない。残るのは本人ではなく、偏見や呪い、戦争の火種だ。これを断ち切るには、教育や交流で偏見を薄め、避難訓練を人が集まる行事に変えて習慣化し、裁判を透明化する必要がある。“神話”をみんなが守れる「決まり」へと作り直す――二度と同じ戦を繰り返さないために。
人神の声は完全には消せない。だからこそルーデウスは覚悟を更新する。「自分で選んだ」という満足よりも選んだ後の責任を重視し、一度きりの正解よりも続けられるやり方を選ぶ。全勝を求めず、生き残りと再起を優先する。それは彼自身を守るだけでなく、仲間や家族を守る共同体の強さにつながった。
ラプラス戦争とは、派手な一騎打ちではなく“世界の大改修”だった。龍神との契約で敵をはっきりさせ、人神の予言には手順で抗い、政治・技術・家族を通じて負けにくい環境を広げていく。孤独な英雄だったルーデウスは、設計者であり管理者であり父として、世界の命運を背負う存在へと変わった。
世界を救うとは――明日も暮らせるように、世界を直し続けること。その答えにルーデウスはたどり着いたのだった。