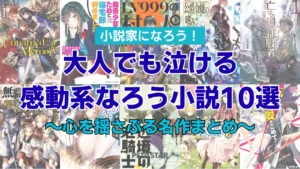第九章:本気で生きた生涯
大きな戦いや救出劇が一段落すると、ルーデウスの日常は次第に「普通の生活」へと重心を移していく。朝の支度を整え、子どもたちの声に耳を傾け、研究を続け、仲間からの相談に応じ、ときには少しだけ出張に出かける。若い頃は「強くなる」ことこそが最優先だったが、今は暮らしを守ることが中心になった。小さな用事をひとつずつ片づけていく日々こそ、彼が手に入れた何よりの宝物だった。
その役割も、かつてのような英雄ではなく、組織や社会を動かす“潤滑油”だった。学園や研究組織で人々が研究を進められるよう背中を押し、段取りを整え、危ない芽を早めに摘む。オルステッドの計画に合わせて情報を集め、各国の窓口と交渉し、約束を文書に落とし、実務を回す。彼は剣ではなく「手順」で世界を動かす“回し役”へと成長していたのである。
仲間たちの姿もまた変わらない。ナナホシは失敗を恐れず実験を重ね、その記録を次へつなげていく。ザノバの工房からは新しい魔導具が生まれ、一人の天才の力が「誰でも使える道具」へと形を変えていく。ルイジェルドの名をめぐる誤解も次第に薄れ、子どもたちは彼の武勇だけでなく「誇りの意味」を学んでいく。ルーデウスは、縁は急がず育て、時間をかけて成果へ変わっていくものだと知った。
その中で、「本気」という言葉の意味も変わっていく。若い頃の本気は、一瞬に全力を注ぐことだった。だが大人になった本気は、明日も続けられるやり方を選ぶことに変わった。強力な魔術よりも整った避難路を、派手な勝利よりも「被害ゼロの撤退」を重んじる。彼は勝つためではなく「生き延びるため」に、世界を少しずつ整えていった。
もちろん、過去の失敗が消えることはない。助けられなかった誰か、言いすぎた一言、遅れた決断。ふとした拍子に顔を出すそれらを、彼は「消す」のではなく「抱えて暮らす」術を身につけた。家族の夕食、子どもの寝息、仲間から届く礼状。生活の手触りが、後悔の角を丸くしていった。
子どもたちはやがて家を離れ、それぞれの道を歩んでいく。魔法を選ぶ子、剣を選ぶ子、まったく別の道を進む子。ルーデウスは口を出しすぎないと決めた。危ない橋には手順を渡し、迷う背中には期限付きの助言を与え、最後はいつも「行ってこい」と送り出す。自分で選び、自分で帰ってくる力を信じるためである。
年齢を重ねると、魔力の回し方も体の動きも若い頃のようにはいかない。しかし判断はむしろ深くなっていった。焦って撃たず、無理を通さず、余白を残す。若さが切り開いた道を老いが安全な道に直していく――それが世代のバトンなのだと、ルーデウスは実感した。
やがて彼は、自分の最期を迎える準備を「特別なこと」ではなく「日常の延長」として整えていった。遺言を短くまとめ、必要な書類を整え、誰が何を引き継ぐかを早めに決めておく。喧嘩の火種は小さいうちに消し、共通の連絡帳に記録を残す。最期の日のために大げさな儀式は必要ない。いつもの日常を、いつも通りに回すことこそ、家族への最大の贈り物だった。
ある朝、彼はいつもと同じように目を覚まし、短い祈りを済ませ、窓を開けた。湯気の立つカップ、遠くから聞こえる笑い声、机の上に置かれたメモ。ノートに「今日もやる」と一行だけ書き、その日の仕事を配り終えると、夕方には子どもたちの顔を見て、妻の手をいつもより少し長く握った。そして夜、静かな寝息のまま、一日を終えた。彼の幕引きは、最後まで彼らしい“段取りの良さ”にあふれていた。
彼が残したものは、伝説の剣や巨大な像ではない。争いを話し合いに変えるための制度、失敗も成功も次につなげるための記録、避難路や点呼といった習慣、そして「力ではなく暮らしを中心に置く視線」。それらは派手ではないが、毎日を支える土台として生き続けた。人々は彼の名前を出さずとも、彼のやり方で世界を回している。
「本気で生きろ」――子どもたちに残した言葉は短かった。本気とは力むことではなく、続けること。誰かを踏み台にせず、明日の自分と周りの人が少し楽になる選び方をすること。それができれば世界はゆっくり良くなる。ルーデウスはそう信じていた。
物語が終わった後も、世界は回り続ける。政治は揺れ、技術は進み、子どもは育ち、誰かが年を取る。ルーデウスの生涯は「奇跡の連発」ではなかった。小さな手直しを途切れず続けただけだ。しかし、その積み重ねが「戦わなくても負けにくい世界」を作った。
最初の一歩は、34歳無職の小さな決意だった。「今度こそ本気で生きる」。最後の一歩も同じだった。「明日のために、今日やることをやる」。彼の物語は派手な花火では終わらない。明日も暮らせるように――世界を少しずつ良くするやり方を、静かに遺して幕を下ろしたのだった。